CYLLENGEブログ
2025.07.01
AIエージェントがシステム部門にもたらす変革と未来展望
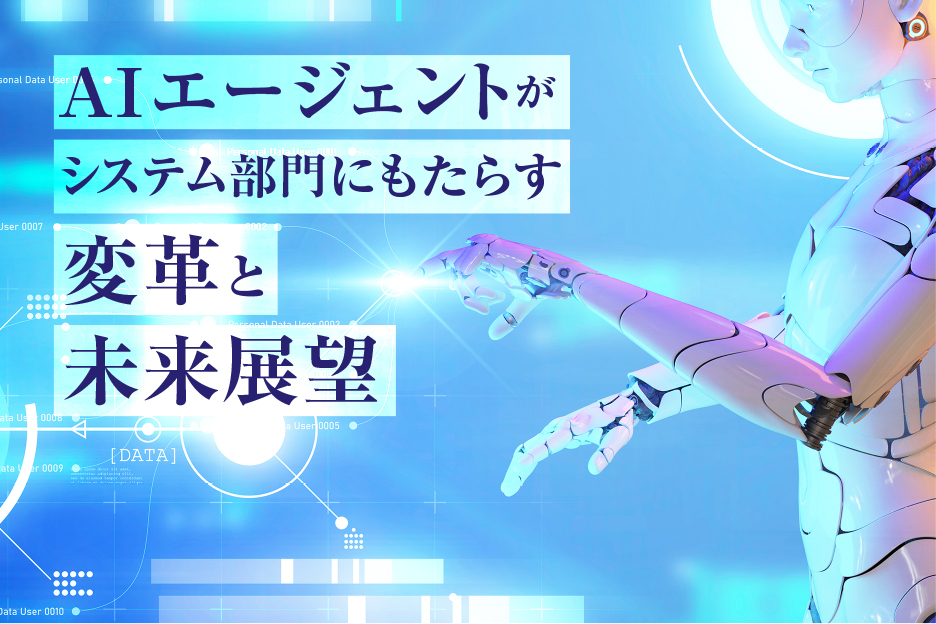
―AIエージェントがシステム部門にもたらす変革と未来展望―
現在、「AIエージェント」というキーワードが注目を集めています。これは、ChatGPTをはじめとする生成AIとは何が異なるのでしょうか?
本記事では、「AIエージェント」の基礎知識から、具体的な活用可能性、導入における課題、そして将来展望までを解説します。AIエージェントが、我々の業務をどのように変え、どのような新しい価値を生み出すのか、その可能性を探っていきましょう。
目次
1. AIエージェントとは何か?なぜ、注目されているのか?
AIエージェントとは、自らが置かれた環境を認識し、設定された目標を達成するために自律的に思考し、行動する能力を持つソフトウェアシステムやプログラムのことを指します。
従来の自動化ツールが事前に定義されたルールに基づいて定型的な処理を行うのに対し、AIエージェントはより高度な判断力、学習能力、そして適応力を備えている点が大きな違いです。
-生成AI-
あらかじめ定義(指令)されたルールに従って応答を返す。
– AIエージェント-
環境に応じてタスクを分解・計画・実行する「能動的な存在」
AIエージェントの理念や研究は、ChatGPTに代表されるLLMの登場以前、1990年代から存在していましたが、当時のトレンドは現在とは大きく異なっていました。
今、これほどまでに注目を集めている背景には、いくつかの要因が絡み合っていると考えられます。
– 大規模言語モデル(LLM)の進化-
ChatGPTなどのLLMが自然言語の理解や推論力を飛躍的に向上させたことで、AIエージェントは人間と対話しながら高度なタスクをこなす能力を獲得しています。
– 計算能力とデータ活用の進展-
クラウドやGPU性能の向上、企業内データの活用が進んだことで、AIエージェントの学習・運用環境が整いつつあります。
– DX推進による需要の高まり-
業務効率化や新たな価値創出を目指すDXの流れの中で、AIエージェントはその実現を支える有力な手段として注目されています。
著名なAI系企業や団体{OpenAIやIBM、Gartner、SoftBank等}が定義を掲げていますが、共通するのは「環境を理解し、タスクを自律的に計画・実行する能動的な存在」であることです。
特にIT部門にとって、AIエージェントは、日々の運用負荷の軽減、セキュリティレベルの向上、そしてより戦略的な業務へのシフトを可能にする鍵となり得る存在です。
反復的なタスクや定型的な問題解決をAIエージェントに委ねることで、私たちはより付加価値の高い業務に注力できる期待がもたらされます。
2. AIエージェントはどうやって実現されるのか?:定義、構成要素、アーキテクチャ
主要な構成要素、そして代表的なアーキテクチャを紹介します。
特に近年の大規模言語モデル(LLM)を基盤としたAIエージェントの構成要素は、いくつかの重要な要素から成り立っていると説明されています。
AI分野におけるエージェントの基本的な定義は、「環境から知覚を受け取り、行動を実行する能動的な存在」であり、その特性は、状況を「知覚」し、「意思決定」を行い、「自律性」をもって「行動」できる点にあります。
-「知覚」-
これは主にエージェントが相互作用する環境との接続によって実現されます。LLMベースのエージェントにとって、環境はウェブスクレイピングやAPI呼び出し、ウェブ検索、ソフトウェア操作、データベースクエリを含むコンピューター環境との連携など…多岐にわたります。
-「意思決定」、「自律性」-
これは主にエージェントの「脳(cerebral core)」として機能する大規模言語モデル (LLM)によって担われます。LLMは、現在の観測、知覚の記憶による情報、および再考による自己改善によって戦略を立て、自律的な意思決定を行います。
-「行動」-
GPT系モデルに代表されるLLMには、Responses API(旧function callingなど)に代表される外部の関数やAPI、コンピューター操作を呼び出す機能が搭載されています。こういった外部呼出しの機能を用いてエージェントは知覚を得るだけでなく自身で能動的な行動を可能にします。
AIエージェントはどうやって実現されるのか? まとめ
AIエージェントには「知覚」し、「意思決定」を行い、「自律性」をもって「行動」できるという特性があり、環境からの知覚、記憶による情報保持、LLMによる推論と計画、再考による自己改善、そして具体的な行動を実行する能力はLLMの組み合わせや外部との連携によって支えられています。
このような特性によって、定常的なタスク実施や専門的な活動サポートへの活用が可能となります。
3. 活用可能性と課題
活用可能性
AIエージェントは、分野や特定のタスクへの特化によって、チャットボットを越えた次の段階の支援が期待されます。
– ワーク/リサーチアシスタント-
科学やITシステムなど特定分野の情報収集や効率化を支援。例えば、膨大な文献からの情報収集・要約、実験データの分析、レポートや論文のドラフト作成までの一連のフローを自動化する期待があります。
– ソフトウェア開発エージェント-
コーディング支援、バグの特定と修正提案、テストケースの自動生成、最新技術トレンドの提供、プロジェクト管理の補助など、複雑化するソフトウェア開発の運用負荷軽減に貢献します。
– 専門業務特化型エージェント-
法律分野での判例検索や契約書ドラフト作成支援、金融分野での市場分析やリスク評価など、高度な専門知識を要する領域での意思決定や業務遂行をサポートします。
課題
– 信頼性と精度の担保-
AIエージェントが提供する情報や判断が常に正確であるとは限りません。誤った情報(ハルシネーションを含む)を生成するリスクがあり、特に重要な意思決定に用いる場合は、事実確認や人間の監督が不可欠です。
– 説明責任と透明性の確保-
AIエージェントの意思決定プロセスが複雑なため、なぜそのような結論に至ったのかという根拠を示すことが難しい場合があります(ブラックボックス問題)。問題発生時の責任の所在を明確にするためにも、判断プロセスの透明性や説明可能性を高める技術が求められます。
– セキュリティとプライバシー-
AIエージェントは業務を遂行する上で、機密情報や個人情報など多くのデータにアクセスする可能性があるため、不正アクセス、情報漏洩、悪意のある第三者による乗っ取り(プロンプトインジェクションなど)といったセキュリティリスクへの対策、および厳格なプライバシー保護措置が不可欠です。
4. AIエージェントの今後と展望
既にエージェントの社会実装は進んでおり、既に実用の段階となっています。
急速な発展を遂げる分野ではありますが、上げた課題も今後数年(もしくは数か月)で改善していく期待は大いにあります。
また、「Agent2Agent Protocol」と呼ばれるエージェント同士でやり取りをするための規格も{Googleより}公開されはじめています。将来的には、人同士が直接コミュニケーションするのではなく、エージェントが代理人としてやり取りを行う未来が訪れるかもしれません。
今後も活用は進んでいくことが期待されるAIエージェントですが、最新動向を正しく理解し活用していくことはDXの未来のために求められることになるのではないでしょうか。
参考:
https://arxiv.org/abs/2404.11584
https://arxiv.org/abs/2401.03428
https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202412/what-is-ai-agent/
https://aws.amazon.com/jp/what-is/ai-agents/
https://openai.com/ja-JP/index/new-tools-for-building-agents/
https://developers.googleblog.com/en/a2a-a-new-era-of-agent-interoperability/
製品情報、ホワイトペーパーなどのお役立ち資料はこちらから▼


